 |
||
 |
||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
はじめに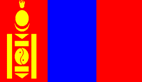 モンゴルに2005年4月から1年間JICAシニアボランティアとして、その後、昨年(2007年)の11月まで1年半は新しい国内航空会社Eznis
Airwaysの立ち上げのお手伝いとして、都合2年半余を過ごしました。 モンゴルに2005年4月から1年間JICAシニアボランティアとして、その後、昨年(2007年)の11月まで1年半は新しい国内航空会社Eznis
Airwaysの立ち上げのお手伝いとして、都合2年半余を過ごしました。その間、暇にまかせてウランバートルの色々な博物館を見て歩いている内に、モンゴルの歴史に興味が湧き始めたので何冊か本を読んでみました。自分の記憶整理の為にと簡単に纏めたものを、友人知人に送っておりましたが、本編はその一部を見直してみたものです。 下記の3冊の本を基にし、日本大使館資料やJICA資料も参考にしています。また折々に自分が見聞きした事柄も書き加えておりますので、誤りも多々あると思われます。 また写真なども色々なウェブサイトから拝借しておりますが、出典が明確なもののみ、その由記載している点ご容赦下さい。 「モンゴルの歴史」 宮脇淳子著 (刀水書房刊) 「チンギス・カーンとモンゴル帝国」ジャンポール・ルー著 (創元社刊) 「モンゴル歴史紀行」 松川節著 (河出書房新社刊) Web百科事典『Wikipedia』
 モンゴルと聞いて思い浮かべるもの 日本とモンゴルの関係は、鎌倉時代の元、フビライ・ハーンによる日本来襲「元寇の役」から満州国建国後のノモンハン事件、モンゴル建国時の関わり、戦後はモンゴルの一番の援助国となるなど意外に長くて深い。 特に私が驚いたのは、戦後ソ連に抑留された50万の日本軍捕虜の一部がウランバートルにも連れてこられて市の中心部の主要な建物建設に従事させられ、その建物郡が現在も健在で立派に使用されているという点であった。 現在では、モンゴルと聞いて我々日本人が思い浮かべるのは大草原の国、チンギス・カーン (ハーンと書く方が実際の発音に近い)、朝青龍、白鳳などのモンゴル力士、さらに我々年配者では蒙古斑というところであろうか。まずはこれらについて触れてみたい。 1.大草原 この大草原こそが、モンゴル民族などの遊牧騎馬民族が3千年に亘って遊牧生活を送ってきた舞台であり、東は満州、西はウクライナ地方、北はシベリア南部、南は内モンゴル自治区などの中国の北半分までのアジア大陸の大半と東ヨーロッパまでを覆っていた地域である。 現在はその大半が農地化されたり、荒野化したりで、本当の意味の大草原と遊牧生活というのは、世界でこのモンゴル高原にしか残っていないと言われている。 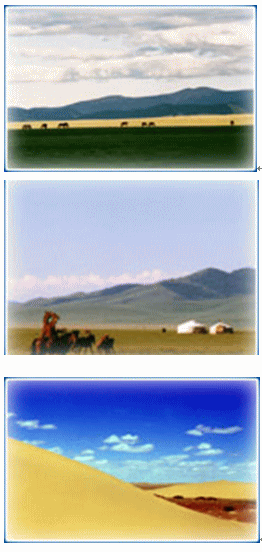 ウランバートルの中心から車で30分も走れば、後はどこまでいっても緑の大草原が延々と続く景色となり、日本の4倍の国土だという広大さが実感される。しかし国土の1/4は中国との国境にまたがるゴビ砂漠で、西は最高4,500mの山岳地帯で占められていて、これらの地域を除いた部分が大草原である。遠くから見ると緑の絨毯のように見える大草原であるが、残念ながら近くでみると草が密生して生えている訳ではなく、荒野の半分位が草に覆われているという感じである。 ウランバートルの中心から車で30分も走れば、後はどこまでいっても緑の大草原が延々と続く景色となり、日本の4倍の国土だという広大さが実感される。しかし国土の1/4は中国との国境にまたがるゴビ砂漠で、西は最高4,500mの山岳地帯で占められていて、これらの地域を除いた部分が大草原である。遠くから見ると緑の絨毯のように見える大草原であるが、残念ながら近くでみると草が密生して生えている訳ではなく、荒野の半分位が草に覆われているという感じである。これはモンゴル高原が平均降水量250mmと日本の1/10近くしかない乾燥した地域のためで、農耕に適する面積は国土の1%程度、残りの大地は草しか生えない草原という訳である。 この草原も緑を保っているのは5月から9月までで、残る季節は荒涼たる茶色の大地で12月から4月までは白銀の世界となる。この肥沃とは言えない草原で牧畜をする為には、草を追って次々と移動しなくてはならないために遊牧生活が始まり、その生活振りは3千年前から殆ど変っていない。 2.チンギス・ハーンは源義経説  義経は頼朝に追い詰められて奥州で果てたことになっているが、この義経が生き延びて大陸に渡ったという説が結構日本で伝えられている。これが全くの虚説だという事は、全ての日本人が承知しているものの、何故かモンゴルに親近感が湧くので今も折に触れ語られることが多いようだ。 義経は頼朝に追い詰められて奥州で果てたことになっているが、この義経が生き延びて大陸に渡ったという説が結構日本で伝えられている。これが全くの虚説だという事は、全ての日本人が承知しているものの、何故かモンゴルに親近感が湧くので今も折に触れ語られることが多いようだ。何人もの日本人が偽書しているが、江戸初期に沢田源内が書いた「金史別本」が最初で、義経が蝦夷から金の国に渡り、その孫が金の騎馬軍団を統帥して中国を攻めたという話である。その後、対馬出身の国学者で森助右衛門という者が、清の史書に「朕の姓は源、義経の裔、その先は清和に出ずる。故に清国と号する」と書かれているという珍説、全くの虚構を発表。 1879年に、後に逓信大臣、内務大臣になった末松兼澄がイギリス・ケンブリッジ大留学中に、差別待遇に怒ってイギリス人に日本人の偉大さを示したいと、イギリス人名で論文「義経=ジンギス・ハーン説」を書いた。1885年に内田弥八という者がこの論文を補強して「義経再興記」を出版。 1924年、小谷部全一郎という者が「成吉思汗ハ源義経也」という書を出版し、日本のシベリア出兵の時代だったので大ベストセラーとなった。 こういう話を好む人は何時の時代にもいる為、密かに伝えられ、特に見知らぬ中国大陸に初めて渡った日本人にとってはこの上ない励ましになったものと思われる。また、今なお日本人のモンゴル人への親近感に大きく貢献しているものと思われる。 3.モンゴル相撲  現在、日本の相撲界は朝青龍を筆頭として関取が10人以上とモンゴル力士に乗っ取られた感すらするが、彼らのおかげでモンゴルでも日本相撲が大人気で、各場所共、NHK衛星実況放送をモンゴル語の解説で放映いる。 場所中は食堂、コンビニなどの売店、空港やホテルのロビーではどこでもこのテレビ相撲放送を流していて、仕事そっちのけで見入っている。 モンゴル相撲は元々、モンゴル兵達がその体力を競うためと余暇のために、何の仕切りもない草原で相撲を競ったもので一番強い者には最高の栄誉が与えられたと伝えられているが、あまりはっきりした記録は残っていないが、2000年位の歴史があるようである。 このモンゴル相撲が西に行ってトルコ相撲、南に下って韓国や日本の相撲になったと言われている。 記録に残っているものでは、清朝皇帝への奉納というかたちで奨励され、18世紀以降に職業力士が養成され始めたという。日本では織田信長が相撲を見るのを好んだと言われるが、現在の形が確立されたのは江戸時代である。 モンゴル相撲を相撲宮殿に見に行ったが、日本の相撲とは大分違い、短いものは10秒程度で勝負がつくものの、時間制限がないため長い勝負が多く、2時間を越す場合もあるという。長くなると途中で選手が組み手をほどいて勝手に水を飲みに行ったりして、しごくのんびりしている。  7月11日の革命記念日を挟む3日間の祝日中に行われる夏の祭典Naadamでの全国大会には500人以上が参加して二日間に渡りトーナメント戦を行う。小さい大会でも100人近くの力士が一日で決勝まで行なう。 強豪力士はシードされているものの、優勝するには7-8回連続して勝ち抜かなくてはならない。このため最初の1-2回戦は10組以上が一度に対戦するのでどれを見ていれば良いのか落ち着かない。土俵のように、ある一定の広さの場所で対戦するのではないため、「押し出し」や「寄り切り」という決め手は無く、また激しくぶつかる立会いもないので「はたき込み」もない。手の平を着いてもOKで投げ技や足技などで相手を倒し、相手の背中や膝から上の上半身を地に付ければ勝ちとなる。 朝青龍、白鵬、旭鷹山などはこちらでは大変な成功者、金持ちで、日本でのイチロー、松井秀樹、中田英などに匹敵してあこがれの的となっている。以前は男女を問わず朝青龍が圧倒的な人気であったが最近は白鵬が超えたようである。両者共、色々なコマーシャルに出ているため、チンギス・ハーンと並んで街の至る所に顔写真入り広告ポスターが貼られている。  なお、引退してモンゴルに帰っている旭鷹山は不動産などの実業家として成功しており、近々ある国会議員選挙にも立候補するという。 このアメリカン・ドリームならぬジャパニーズ・ドリーム実現のため現在400名近くの若者が日本の角界入りを目指して頑張っており、モンゴル関取衆が資金的な援助を行っているそうである。彼らのハングリー精神からして、大相撲が乗っ取られるのはそう遠い将来ではないように思われてならないが若い日本人有望力士の出現を期待したい。 モンゴル帝国建国800周年であった一昨年に大相撲モンゴル興行が計画されたが会場の都合で実現できなかったが今年は実現される予定とのこと。大変な人気を博すことであろう。 4.蒙古斑 モンゴロイドという人種分類があるが、これはドイツの人類学者が1800年頃に人類をコーカソイド(白人種)、ニグロイド(黒人種)、モンゴロイド(黄色人種)、アメリカ先住民(インディアン)、マラヤ人(太平洋人種)の5つに分類したもので、モンゴロイドはヨーロッパで歴史上最も知られていた黄色人種「モンゴル人」から生まれた言葉である。なお、コーカソイドというのは「コーカサス」から生まれた言葉だが、ロシア人はアジア的な呼び名だと気に入らずに「ユーロペオイド゙」と言い換えている。 日本人の赤ん坊のおしりにある青あざが蒙古斑と呼ばれるため、日本人の祖先はモンゴル民族だと思い込んでいる日本人が多いが、直接の関係があるとは実証されていないようである。 明治時代に日本に来たドイツ人医師が、この赤ん坊のあざを見て、ドイツで生まれた人種区分の「モンゴロイド」の言葉から「モンゴリアン・スポット」と名付け、この日本語訳が「蒙古斑」で、民族的な繫がりがあるという証明ではないようだ。 - つづく - かど のぶゆき、 |
|||||