| |
半世紀前の型式証明
―YS-11の頃―*
元運輸省航空局航空機検査官
藤原 洋
*本記事は『航空と文化』(No.107) 2013年夏季号からの転載です。
|
2013.12.25 |
|
| |
|
|
| |
具体化の悩み
私が1956(昭和31)年に航空局に奉職して間もなく、それまでの DC-3などの国内ローカル線旅客機の後継機を国産旅客機でという機運が高まっていた。この推進役は通産省だったが、運輸省も、数年にわたって、旅客機の安全性研究に補助金を提供するなどしてこの方針に協力していた。私も1956(昭和
31)年の冬 3ヶ月ほど、運輸技術研究所(現在のJAXA)での DC-3 模型の風洞試験に参加した経験がある。
それまで、日本で型式証明を取得した航空機はベル 47 やセスナ L-19 などのライセンス生産機であり、実質的な証明作業は証明記録と安全基準(耐空性審査要領)との突き合わせであったと思われ、旅客機の審査を行ったことは全くなかった。
国産旅客機計画がいよいよ現実化し、YS-11の型式証明申請書を受理する段階になると、私たちの仕事は大きく変化し、旅客機に適用される安全基準・耐空性審査要領第Ⅲ部(飛行機輸送
T)の具体的な証明方法について、一から勉強を始めなければならなかった。
この勉強の素材になったのは、AGARD* Flight Test Technique Series の文献、ダグラスDC-6Bの型式証明記録(飛行試験データ)、英国の Civil Aircraft
Inspection Procedure などであった。YS-11に適用される耐空性審査要領は、DC-6B(写真1)に適用されたものと内容が同一であったことから、DC-6Bの記録や実機がシステム設計を考える上での良い参考資料になった。
* Advisory Group for Aerospace Research and Development の略。NATO に属した機関。 |
|
| |

写真1 ダグラス DC-6B。YS-11の型式証明の際に良い参考資料になった。
(鈴木宜勝氏提供)
|
|
| |
私が担当した部門は、飛行試験の最も基礎的な部分に当たる、速度計・高度計系統の誤差、失速速度、離着陸距離の計測などであった。
文献を読み、ダグラス社の実施方法を推測できても、問題が解決したことにはならなかった。第二次世界大戦後の日本で民間機の本格的な試験飛行やその計測を行った実例ほとんどないため、外国の事例をそのまま準用することは困難で、代替方式をとらざるを得ない場合もあった。
丁度この頃、英国でターボプロップ双発旅客機が開発され、英国航空局(ARB)の審査が行われていた。アメリカとはかなり環境の異なる国の審査方法も参考にしようと、英国航空局で研修中であった検査官に、毎週のようにエアレターで質問状を送り、調査を依頼した。検査官の根ほり葉ほりの質問に、先方から「おまえは日本の産業スパイか」と嫌みを言われるほどであった。
実用化までの苦難
飛行試験が開始されるまでに、機体強度等を証明する各種の試験が行われた。写真 2~7 は主翼静強度試験、胴体疲労試験、胴体損傷試験(通称ギロチン試験)、鳥衝突試験、着陸装置強度試験など、大きなテーマの中から選んだものである。
YS-11原型 1号機は飛行をはじめてみると、いくつもの大きな問題が明らかになった。中でも最も大きな問題は、横安定の不足、補助翼の効き不足、方向蛇の操作力過大、前脚の滑りなどであった。
YS-11はSTOL性能を最大限に発揮させるために、フラップ幅を非常に大きく取ってある。したがって補助翼幅は小さく面積も小さい。小さな補助翼で運動性を発揮させるためには、許容される範囲で静的横安定を弱くするというのが基本的な設計方針であり、東大航研で行った風洞試験では主翼上反角4度19分でOKということであった。しかしながら、実機の飛行結果は芳しくなく、実機が完成する頃になって三菱重工が行ったスラット方式(機体正立)の風洞試験結果でも安定不良という結果となった。旧来の模型を裏返しにする釣り下げ方式の風洞試験では、実際よりも良い値になるという経験則が十分に生かされなかったのかも知れない。
この対策として、主翼上半角を 2度増し、補助翼面積を増加するなどの思い切った改造が行われた。上半角の増加は、内翼と外翼接続部に 3角形のシムを挟むという方法で行われた(写真 8)。
また、フラップ幅を左右それぞれ 500 mm短縮し、それを補助翼幅に振り向けるとともに、翼舷を後方に 100 mm張りだし、厚みを増やすなど、補助翼の効きを強化させた。
方向蛇の操作力過大及び低速時の流れに対しては、垂直安定版にボルテックスジェネレーターを取り付けるなどの対策を試みるなどしたが、最終的に、当初のバランスタブ操縦方式から、スプリングタブ操縦方式に改めることで解決した。
前脚滑りには、主脚脚柱を4度後方に傾け、主車輪位置を100 mm後退させ、前輪の分担荷重を増加して対応した。
機体表面の気流剥離にも悩まされた。客室に時々軽い振動が伝わってくることがあり、これは、気流の剥離による振動と考えられた。そこで、機体表面に気流糸を貼り付け、随伴機から詳細に観測したところ、主翼の胴体付根フィレットと、主翼上面のエンジンナセル後方に大きな剥離現象が認められた。この対策として胴体付根フィレットを大きくし、主翼上面のエンジンナセル後方に整形フィレット(通称三味線バチ)を取り付けた(写真 9~10)。
|
|
| |
|
| |

写真2 主翼の静強度試験。最終的には破壊するまでの荷重を加える。(写真2~7は和久光夫氏提供)

写真3 胴体の疲労試験。水槽の中に入れ、水圧で胴体内部の加圧・減圧を繰り返す。破損した場合、その部品の回収が容易なのが特徴。

写真4 通称ギロチン試験。胴体外皮が何らかの原因で損傷しても、一区画の損傷で収まることを証明するもの。

写真5 ギロチン試験で外板が損傷した試験用胴体。

写真6 鳥衝突試験。設計巡航速度で 4 ポンド(約 1.8 kg)の鳥が風防に衝突しても安全に飛行できることを証明する。

写真7 前脚の着陸装置強度試験。車輪を着陸速度に相当する回転速度で回転させたまま、重りをつけて落下させる。脚柱は後方に大きく曲がり、その反動で前方に跳ね返る。

写真8 上は飛行当初の状態、下は上半角を2度増加させた状態。(下郷松郎氏提供)

写真9 気流糸試験。航空宇宙技術研究所(NAL)のビーチ双発機から観測した。(幸尾治朗氏提供)

写真10 エンジンナセル後方の整形フィレット、通称三味線バチを取り付けた試作1号機。(和久光夫氏提供) |
|
| |
エアラインからの苦情
このように、ひとつひとつ問題を解決し、試作機 2機による試験飛行を2年近く続け、1964(昭和39)年8月25日に型式証明を取得、翌年春頃から日本国内エアラインへの量産機納入が始まり、世界に誇る新型旅客機として華々しくデビューした。ところが、早速いくつもの問題が露呈した。
運航を開始して間もなく、梅雨時期に突入した。途端に苦情続出、フレッシュエアー出口をひねったら、水が飛び出し Yシャツが茶色になってしまった、というのが殆ど。スチュワーデスは雑巾を持って機内を走り回るという珍事となった。口の悪い週刊誌は
YSに乗るときは機内で傘を差せとまで揚げ足をとる始末。この原因はエアコンのウォーター・セパレーターの能力不足で水分除去が追いつかなかったためだった。また、エアステア(搭乗タラップ)を上げると溜まっていた雨水が機内に流れ込んだということもあった。考えて見ると、約
2年の試験飛行期間中、雨が降ると試験を中止し、機体を格納庫へ収容してきた。これは計測データの信頼性を保つことと、万一の事故に備えたためだが、これが[雨に弱い箱入り娘]に育ててしまったと反省している。YSの最終試験として、エアライン運航を模した約
150 時間の実用試験も行われたが、梅雨時運航を条件に加えてはいなかったと記憶しており、日本の梅雨の恐ろしさを再認識させられる結果となった。
飛行試験の間には起こらなかった不具合がいくつも発生した。無線機冷却ファンが 10時間も持たずに故障する。新品に交換してもやはり短時間で故障してしまう。ところが、試作機にはこの種の故障を経験したことがなかった。試作機と、エアラインの飛行時間の相違がこの問題の根底にあるのかも知れないが、製造会社はその不具合対策を渋った。困ったエアラインは新造機を受け取ると、すぐに自社で部品変更を含む改造を行い、再び航空局の検査を受けた後に事業機に組み込むという事態が何機か続いた。私もこの検査を担当し、エアラインから強烈な嫌みを言われたことを記憶している。不具合対策の遅れはエアラインにとっては死活問題であることを忘れてはならない。
現在、世界の航空界の関心事になっているボーイング 787型機のバッテリー・トラブルの話を聞くたびに、[ボーイングよお前もか]、[この道はいつかきた道]という思いに駆られる。
日米の規則解釈の相違
防除氷装置の是非を巡って航空局と米国連邦航空局(FAA)との間の見解が異なり、大きな問題となったことがある。NAMC(日航製)はこのシステムをDC-6Bに倣って設計し、航空局はOKとしたが、米国にこれでは不適合と判定されたしまった。航空局は、同一基準で設計された航空機に対して、不公平ではないかと食い下がったが、FAAは主張を曲げなかった。
当初のYS-11(通称 -100型)は、左右主翼内にそれぞれ燃焼式ヒーターを備え、ここで発生させた熱風を主翼や尾翼前縁に通して、翼表面の凍結を防ぐ「防氷装置」を備えているが、片側が故障した際に他の側から熱風を供給できないというのが、不適合の理由であった。不適合の理由は理解できるが、同一基準にたいし、適用に差を付けるのは、規則に忠実なアメリカとは思えない。私は参考にした
DC-6Bの装備が基準を満たしていなかったのではないかと推測している。
この要求を満たすには、クロスフィードとしてのダクトを胴体の中に貫通させればよいが、再度、胴体の疲労試験を行わなければならいことになる。これは実質的に不可能と判断され、量産50号機以降のYS-11A-200
型は翼前縁部にゴム・ブーツを付ける「除氷方式」に改め、FAAの承認を得た。しかしながら、このために翼の翼型が大きく損なわれ、運用可能高度がかなり低くなってしまった。YS-11があと
5,000 フィート高い高度を飛行できれば、乗り心地が良くないという批判はかなり減少したであろうと考えると、残念でならない。
型式証明の集中
YS の型式証明申請に続いて、三菱重工から MU-2、伊藤忠航空整備から N-62、富士重工から FA-200と 3機が相次いで申請された(表1、写真11~13)。
航空局としては最初のYSで色々経験したため、審査は比較的順調に推移したといえるが、申請者側も順調だったというわけではない。MU-2の場合は、設計目標自重が大きく超過した上に、エンジンの利用可能出力が10%ほど少なくなるというダブルパンチを受けてしまい、大幅な設計変更を余儀なくされた。このため、当初申請の
MU-2Aは型式証明を取得したものの、販売はせず、翼幅を約 1 m 延長、翼面積を増加、胴体への取付け角を大きくし、より強力なエンジンに換装したMU-2Bを販売することとなった。
N-62では大きな改造は少なかったが、エレベータの効き改善のために逆キャンバーにするなどの対策が採られた。また、量産機は原型機より胴体長さを
10 cm 長くし、座席スペースを拡大、乗り心地改善を図った。エレベータの効き改善はFA-200に対しても同様な対策が行われた。
|
|
| |
| 表1 YS-11 とそれに続いた国産機の初飛行日と型式証明取得日 |
| 型式名 |
原型初飛行日 |
型式証明取得日 |
日本航空機製造 YS-11
(双発ターボプロップ旅客機) |
1962(昭和37)年8月30日 |
1964(昭和39)年8月25日
|
三菱重工 MU-2
(双発ターボプロップ機 6 人乗り) |
1963(昭和38)年9月14日 |
1965(昭和40)年2月18日
|
伊藤忠 N-62
(単発レシプロ機 4 人乗り) |
1964(昭和39)年8月8日 |
1965(昭和40)年9月6日
|
富士重工 FA-200
(単発レシプロ機 4 人乗り) |
1965(昭和40)年8月12日 |
1966(昭和41)年3月1日 |
|
|
| |

写真11 三菱 U-2A双発ターボプロップ機。フランス製エンジンを装着、量産機 MU-2Bはアメリカ製エンジンに変更した。

写真12 伊藤忠 N-62。セスナ機の部品を多用したが、コストが引き合わず試作 1機、生産機5機のみで断念した。

写真13 富士重工 FA-200。曲技飛行から旅行用までと、幅広い使い方ができるのがセールスポイント。約300機販売された。 |
|
| |
型式証明用機器の活用
本格的な型式証明の実施に備え、離着陸距離測定用カメラ、計器指示記録用カメラ、気流糸観測用カメラ、フィルムモーションアナライザー(撮影記録解析装置)、標準ピトー管、曳航静圧管装置などを購入した(表2、写真14~15)。
私はこれらの多くの機器を使用したことがあるので、その活動の一端を紹介する。
離着陸距離測定用カメラは、英国ヴィンテン社の製品。商品名はテイクオフカメラ。撮影画面には、方位角及び時計も記録される(写真16)。
|
|
| |
| 表2 型式証明用機器 |
| 離着陸距離計測カメラ |
英国ヴィンテン社製、70 mm フィルム使用
駒撮り、毎秒 1~5 駒撮影可能 |
| 計器記録用カメラ |
35 mm ムービーカメラ
連続及び駒撮り |
| 気流糸観測カメラ |
16 mm ムービーカメラ |
| フィルムモーションアナライザー |
70、35、16 mm フィルム共用解析装置
クロスポインター操作により精密読取りを行う |
標準ピトー管
(スウィベルピトー) |
静圧測定装置と組み合わせて速度計等の較正に用いる |
| 曳航静圧管装置 |
ダグラス社製、マッハ1 まで使用可能 |
|
|
| |

写真14 ヴィンテン・テイクオフカメラ。離着陸距離を測定する。

写真15 フィルムモーションアナライザー。上部のリールを交換することにより、70、35 及び 16 mmフィルムの読取り・解析ができる。

写真16 ヴィンテン・テイクオフカメラで撮影した画像。下に方位角、左下に時計が写し込まれる。
|
|
| |
当時の規定では、離着陸性能は、実測した空港の標高から 6,000 ft(約 1,800 m)高い空港まで計算により拡大してよいことになっていた。このため、わざわざ松本空港(標高約
700 m)で実測を行ったが、標高 2,500 m 以上の空港での運航は不可能だった。そこで、南米デモフライトを含め、1967(昭和42)年4月、ペルーのアレキーバ空港(標高
8,410 ft=約 2,560 m)で、検査官立ち会いの下、離着陸試験を行った。この試験のためにヴィンテンカメラが日本から空輸された。
このカメラは型式証明以外の目的にも広く使用された。手元に記録の残っているものを列挙すると、グラマン・グース水陸両用飛行艇(JA5063)の耐空検査(写真17)、デハビランド・ヘロンを新明和工業で改造したタウロンの性能測定などである。 |
|
| |

写真17 ヴィンテン・テイクオフカメラはグラマン・グースの新規耐空検査にも使用された。これはPS-1開発を目的として試作されたUF-XFの性能測定の予行演習であった。
|
|
| |
計器記録用35 mm ムービーカメラは、試作1号機の客室内に増設された計器板の指示値を記録するためのもの、16 mm ムービーカメラ(広角レンズ付き)は射撃訓練用のガンカメラから発展して商品化されたもので、外気に曝される機外取付けができ、気流糸試験などの撮影に用いられるものである。
速度計や高度計の較正には標準ピトー管と曳航静圧管装置を装着して飛行し、飛行速度や航空機の形態(フラップ角・着陸装置の上下等)を変えて計測し、標準ピトーによる指示値と、本来計器の指示値との差を計測する。計器の誤差計測は、飛行の最初の段階で行われる最も重要な作業で、以後の飛行データはこの時の誤差値で修正されることになる。
標準ピトーは装着する航空機によって装着位置やブームの太さ長さが変わる。したがって、航空局が用意したものは先端の矢羽根部分と中に組み込まれた計測装置のみで、ブームなどは航空機メーカーが作って取り付けることになる(写真18~19)。
これらの試験装置は一連の型式証明試験終了後、長らく倉庫に眠っていたが、現在は、国立科学博物館の所有物となって、大事に保存されている。YS-11の引退を記念した展示会で、これらの装置が展示されたことがある。
|
|
| |

写真18 標準ピトーと曳航静圧管装置を装着飛行しているN-62。計測時にはトレーリング・コーンが付いたチューブの長さを延長する。

写真19 MU-2の機首に装着された標準ピトー管。機首から長く突き出しているので、特別に長い専用トーイング・バーで地上曳航した。
|
|
| |
(おわり) |
|
| |

元運輸省航空局航空機検査官
藤原 洋(ふじわら ひろし)

|
|
| |
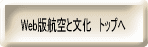
Copyright (c) 2013 Japan Aeronautic Association All
Rights Reserved
|
|
| |
 |
|

