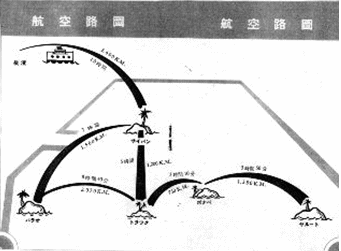飛行艇パイロットの回想
-横浜から南太平洋へ- (7)女護ケ島探問記

大日本航空海洋部横浜支所航空路 昭和17年作成
1. 南洋群島の佇まい
昭和17年の正月を迎え、国内ではお屠蘇気分の抜けきらないうちから、破竹の勢いで帝国陸海軍の進攻は、連戦連勝を誇っていた。フイリピンの首都マニラ陥落、そして、はるばる赤道を超えた南太平洋の、米軍の生命線であり、難攻不落といわれた軍港基地ラバウルを占領したことを、大本営は軍艦マーチを流しながら発表し、日本国内が、すっかり戦勝気分に浸っていた。
大日本航空も急遽、第2運営局を設置し、海軍懲用第5輸送隊(横浜)と第6輸送隊(サイパン・主としてトラック島基地第4艦隊勤務)の編成業務が開始されることになった。
大量航空輸送時代が到来し、海軍では、九七式大艇に代わる軍用の二式超大型飛行艇製造に要求された性能は、桁外れなものだった。敵の哨戒機にまさる巡航速度は時速400km以上、航続力は、今までの性能をはるかに凌ぐ7000kmというものだった。
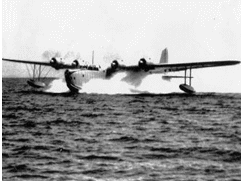
九七式大艇に代わる二式超大型輸送飛行艇
この成功とともに大日本航空には、これを改造し、客席を二階建てにした民間輸送機『二式超大型飛行艇』の配置が決定された。翌18年からの運航に間に合うように、指名された乗員達が交互に海軍に委託され、新機種拡張の飛行訓練が運航と平行して行われた。
広大な太平洋に点在する南の生命線である南洋諸島の島々は、そのほとんどが周辺を取りまく珊瑚環礁で囲まれていて陸上機のように滑走路建設を必要としなかった。隆起した珊瑚環礁が、ちょうど、天然の防波堤となって、太平洋の荒波をさえぎっており、しかも珊瑚環礁と島との間は湖面のように静かだった。それに、赤道直下の恒風である東風に平行して、東西に展開した1,500m以上の水上滑走路となる、天然の飛行場が展開していた。広い太平洋の島々が、そのまま大飛行場であり、滑走路となった。
この島々を結べば、敵にもっとも近い場所に基地として選ぶことができる。陸上機ではとうてい不可能な、最前線航空基地を即座に設置することができ、ただちに緊急輸送ができる大艇の魅力は絶大だった。無制限に離着水に使用できる湾をもつ島国である日本本土と、南洋諸島を結ぶ飛行艇は、最悪の不時着の場合でも、いたる所の島を代替空港に選定できるので、一層の安全運航が確保され、ますます活躍の場が多くなり、注目の的となっていった。前線へ、前線へと、飛行艇は真っ先に飛び立ったのである。
余談だが、川西飛行機製作所は、極秘裡に横浜からハワイまで300人以上を輸送できる、長距離飛行艇製作の構想をもっていた。軽量化のために内装は木製で、エンジンは前後にプロペラがある(タンデム式)計12発を装備した超大型飛行艇の設計にとりかかり、製作の段階へ移っていたが、戦雲の広がりとともに中止になった。現在のジャンボ機の夢は、すでに日本人の手によって設計製作への段階にあったのである。
連戦戦勝に酔った帝国陸海軍は無鉄砲に進攻するだけの、バブル時代の布石となっていった。本土から何千キロも離れた最前線基地に対しての、厖大な兵站物資の補給ないし補強がなおざりにされ、結果的に足元を固める戦略が無視され、逆に悲惨な道へと突き進んでいった。
我々も海軍徴用輸送機として、定期便以外にフライトの指令が慌ただしく多くなり、今日はラバウルか、明日はヤルート島か、それが極楽島か地獄島かわからない。どうせ前線にパラダイスなどあるはずはないが、トランク1個をぶらさげて、浮雲のごとくさすらい、毎日、南方の島々を飛びまわった。南洋の孤島でも、島によっては多少趣が変わっていたのが、せめてもの慰めだった。
「明日はお立ちか、お名残惜しや」の歌の文句じゃないが、
「明日は飛び立つパラオに思い出と名残を残して・・・」
などと言おうものなら、いい彼女でもいたのでは?と早合点されそうだ。当時のパラオ島には日本の統治下にあり、南洋庁の所在地で、南洋諸島の中でも、とくに開けており、経済活動の盛んな島だった。
当時としては、まだまだ新鮮な果物が十分食べられ、きれいな若い日本人ウエイトレスに、心暖まるサービスをしてもらい、そのうえ南洋のそよ風にのってムード溢れる軽音楽が流れる喫茶店もある近代的な街であった。夜ともなれば、立ち並ぶ料亭には蛇味線のはやしに合わせた沖縄出身の芸者衆、軍人軍属、民間人、たちの歌声の大合唱が流れていた。
海岸の椰子の木陰では、月明かりの下で群れ楽しむ、ミクロネシアンとヤマトンチュウ(内地の人)の若者たちは、ウクレレの音に合わせて歌い、そして踊り、夜が更けるのも忘れ、南洋の涼しい夜を十分楽しんでいた。戦時中の夢のような極楽島の一つだった。
2. 不時着水
あるとき、われわれは九七式大艇で、パラオ島からトラック島へ直行のフェリーフライト(次の飛行予定の関係で乗客なしでの飛行)に乗務することになった。まだ飛行艇では飛んだ事のないパラオ~トラックの直行コースを航空図上にプロットし、快晴のなか、鼻歌交じりに快調に飛行していた。
海軍航空本部によって海洋図から航空図が製作されていた時代には、多分、飛行する予定が皆無だったのか、それとも技術的に製作が困難だったのか分からない。いずれにしても綿密な必要がなかったのだろう。とにかく我々が全幅の信頼を寄せている日本海軍が誇る航空図には、全く明記されていない島々が、次々とコース上に現れてくるではないか。なんと新発見?の島々の多いことか。

パラオ~トラック直行、白マーク位置が女護島
その昔、ドイツやスペインの船乗りたちに語りつたえられていた『世界の航海の難所』というのも十分頷けるというものだ。島また島の海上には、なんと航空図にのっていない島が十数島以上にもなった。
「一体、どんな島民がこんな小さな島々にいるのかなぁ、どんな生活をして住んでいるのかなぁ、それとも無人島なのかなぁ」太平洋の新鮮な発見とともに、下界の不思議な光景をボンヤリと眺めていた。
いきなり機関士の悲愴な大声が鼓膜に飛びこんだ。「あっ、2番エンジンの油温計があがってきた。あれッ、油量は減ってくるぞッ!」ギクッとして我に返り、すかさず機関士が指さす計器に目をやる。「駄目だッ、このままじゃエンジンが焼きついて火災になるぞ。2番エンジン・カットだ!」
すかさずスイッチを切ってエンジンを止めたまでは良かったが、フェザー装置(空気抵抗を最小限にするためプロペラを風の流れに垂直に止める装置)がない時代の悲しさ、プロペラは無情にも大風車のごとく空回りをつづけ、大きな空気抵抗となる。速度を保つために機体を降下姿勢にした。他のエンジンをふかして、速度維持をすれば、高度維持が困難な状態になってしまった。大切な残りのエンジンの酷使によって、もし万一、残りの一発でも故障したら万事休すだ。
「よしっ、とにかく直ちに不時着しよう。そしてプロペラを縄で縛り付け、固定して空回りを止めるのが先決だ」機長はついに不時着水を決断した。「了解、徐々に降下姿勢をつづけながら低空になるまでに、不時着する最適な珊瑚礁の島を見付けよう」
幸いにして海は凪いでおり、滑空で行ける前方に珊瑚礁の中に椰子の木が茂っている、真っ白な砂浜のある弧島があり最適な不時着場所が見付かった。
「ようし、あの島にしよう。それっ」
3. 夢の楽園?
無事、着水に成功し、白い砂浜へ向かって滑走をつづけた。島を見ると椰子の木陰から人影がチラチラ見える。「ありゃ、こんなところに人が住んでいる。無人島じゃないぞ」感心しながら停止し、錨を下ろした途端にカヌーがふっ飛んできた。「皆さん、ようこそいらいしゃいました。私達でできる仕事は、遠慮なく申しつけていただければ、ちゃんとやります。とにかく早く上陸して下さい」
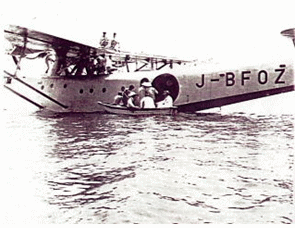
砂浜のまえに繋留して、事情を報告
日本語が耳元に飛びこんできたのには、ビックリ仰天したものだ。用件は後程ということで、早く早く急がされながら、プロペラの縛り方を指導し、完了を見届けて上陸と相成った。
驚いたことに、誰もかれもが、胸が突き出た女性で、長い黒髪を風になびかせ、タコの木の葉っぱの腰巻きが、格好よく腰に巻かれていた。なんだか友好というより、異様な雰囲気の笑顔で迎えられたが、それでもホッと一息ついて見渡すと、7、8人づつ一列になり、それが行儀よく3列になって、われわれを囲み、不思議そうにジロジロと上から下まで眺めまわしている。
そのうち、明らかに軍人と思えるもう一人の日本人のオジサンが、フンドシを締めた真っ黒に日焼けした顔で、ユックリと近づいてきた。「やぁ、ご苦労さん」と、オジサンはニコニコしながら、懐かしそうな親しみのある顔で、手を差しのべてきた。しかし、軍人特有の精悍さがまるでない。握手する態度は、日焼けした顔だが、どことなく物静かな動作だった。
「すみませんがこの島は女が酋長です。是非、挨拶したいと、先程から大変喜んで待っておられます」と、さっさと先に歩きだした。列をなしている彼女たちのウインクと笑顔の中を、かき分けるようにしてうしろに従ったが、どうも奇妙な雰囲気だった。案内された所は、小さいがよく整頓され、掃除がゆきとどいた丸太小屋が点在している。その中でも、一番美しい、なんとなく色気の漂っている明るい感じの小屋が目にとまった。
「この御殿のなかに、われわれの女王と崇める女酋長がおられます。わたしの合図で一人ずつお呼びしますので、それまで次の人は、合図するまで待っていて下さい。寂しい島ですから、会って大いに慰めてやって下さい。あなたが最初にどうぞ。くれぐれも優しく丁寧にお願いしますよ」
一番若いナイス・ボーイ(イケメン)の通信士くんが、指名された。7人の乗員は勝手に2組に分けられ、年輩の機長と機関士の熟年組は、隣の次の小屋に案内された。酋長の方は通信士の次が私の番だった。合図があった時には、十分ユックリ優しく話し合ったのか、ニヤケタ顔で、何回も頭を傾けながらでてきた通信士くんは、何か考え込んでいる様子だった。
いそいそと中に入ってみると、女酋長がニコッと妖艶な笑顔をふりまきながら、手を差し延べてきた。それはそれは柔らかで、情熱に燃えている感触だった。なかなか握った手が離れなかった。一応、身振り手振りで、丁寧に挨拶をしてでてきた。「ナヌッ、それだけかッ?」というなかれ。本当に手を握っただけですぞ。
外ではくだんのオジサンが待っていた。「あんたはどうしてこんな孤島にきたのですか?」「いやぁ・・・・実はわれわれの潜水艦が、異常な潮流に流されて座礁してしまったのです。私は衛生兵を兼ねていましたが、そのときに生き残った者は5名でしたが、残念ながら負傷を負っていて、2名だけが生き残ったのです」と涙ぐんだ。そして次のようなことを話してくれた。
「この島の人口は25人くらいで、男といえば2人の島民と私達2人の4人だけです」たまりませんよ、と言わんばかりの顔が気になる。「生まれてくる子供は女ばかりです。きっと特殊な強い流れの潮流が島を囲んでいるので、われわれの潜水艦も座礁の羽目となったのです。ここで採れる魚や野菜は、どうも酸性かアルカリ性か分かりませんが、一方に偏っているらしいですよ。それで不思議なことに、一年のうちの決まった季節になると、強かった潮流が弱くなる時季があり、そのチャンスを見逃さずに、近くの島からでしょうが、たくましい青年たちが荒波を乗り越えて、カヌーで漕ぎつけてくるんです。その後はご想像どおりのシーンが展開されるのです」
したり顔のオジサンの話はつづく。「十分楽しんだあとは、再びカヌーに乗って帰っていくのです。あなたたちも、隣の島へでも不時着していれば、それこそ野郎ばかりで、色気もなにもあったもんじゃない。まさか虐待されるようなことはないでしょうが、多分居心地は悪いでしょうし、運悪くひどい目にあったかも知れませんよ。もっとも、私たちも同じ運命だったって訳です。それにしても、女酋長には、今度こそ是非、立派な大和男の子の血が混ざった、男の子孫を産んでもらいたいもんですよ。ヘッヘッヘ、それから機長さんたちの挨拶されたのは、女がしら(大奥の局)で、この島の総ての権限をもっている、うるさいヤツなんです」
オジサンは自分のしゃべっていることに陶酔しているかのよう。「でも熟年の素晴らしい男性が顔をだしていただいたから、さぞかしご機嫌だったでしょう。ここでは機長とかなんとかいう階級は、どうでもいいのです。」お陰で大変助かりましたといわんばかりだった。このオジサン、長い間、その大奥の権力者の局とやらに、サービスを供応されていたのかも知れんぞ、ウッフフフ、何となくやにさがってしまう。これぞ男天国、でもねぇ、毎日々々何の変化もない生活で、女性に仕えるばかりだもんねぇ。このオジサンの元気のないのも分かるというものだ。
「どうでしょうか皆さん、今晩は、私に免じてお泊りになっていただけませんか?貴方がたにも私たちにも、こんなチャンスは二度とありませんよ。全員、大歓迎です。島を代表して申しますが、助けると思って、『日本男児ここにあり』というつもりで張り切って下さい。お願いします」
オジサンは、真剣になってわれわれを口説きだした。「いやぁ、有難うございます。大変お世話になりました。残念ながらトラック島に、一刻も早く帰らないと、やぼったい海軍航空隊や大日航の連中が、人の気も知らずに心配しているでしょう。ところで、どうでしょうか、もしよければ貴方たちもわれわれと一緒に乗って、日本へ帰りませんか」こちらも気の毒になってしまった。
どんなに喜んでくれるかと思いきや、「ご厚意は大変感謝します。わたしの家族は横須賀に住んでいますが、潜水艦を座礁し、破壊してしまった責任もありますし、わたしたちは、もう、とっくに帰還を諦めており、今は、内地への未練も希望もありません。この女護ヶ島で、たくさんの女たちに囲まれて骨を埋めるつもりです」
オジサンは目を潤ませてながら、シッカリと一人ひとりの手を力一杯にぎりしめた。モテモテ通信士くんだけは、「そうでしょうねぇ、同感します。本当に同情します、わたくしだけでも残って、何日でも泊まりたいのですが・・」と本気に真剣な顔で覚悟したようにとれる言葉を吐きながら、真面目くさって、特別に強く両手で握手を交わしていた。
生き残りの潜水艦のオジサンたちと島の愛する女性たちに、後ろ髪をひかれる思いの未練を断ちきって、三発エンジンで離水して上昇しながら、【永遠に平和な女護ヶ島であれ!またきっと来るぞーッ】と、心のなかで叫びながら、大きく翼をふって、一路、トラック島へ向けて直進し帰路についた。
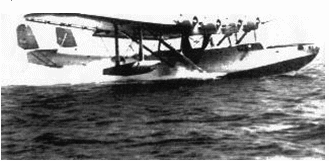
三発エンジンで離水トラック島へ直進
4. 残念!再発見不可能
トラック島へ無事帰還し、ことの経緯を航空隊基地司令に報告して、夢のような楽しかった飛行も終わりとなった。と自分の部屋へ帰って一段落していると、司令が呼んでいるという。今、報告を終えたばかりなのに、何事ならんと、不審に思いながら司令室に顔をだした。
「この度はご苦労さん、まぁ座って一杯やりなさい」テーブルの上には一升瓶がおいてある。日ごろ、いかめしく気取っている司令の風向きが違う。わざわざ酒を注いでくれる司令なんて初めてだ。
「ところで越田くん、そのー何かねぇ、そこの島とやらは、水上偵察機で往復できるかねぇ?」【ははーん、司令どのは、島の場所を詳しく知ろうとしているな。さきほど、報告したときには部下の手前、無関心の体を装おっていたが、こんな司令なんかにいかれてたまるもんか】とっさに言葉をかえした。 「さぁ、無理かもしれません」
我ながらうまいことをいったもんだ。やれやれ、これでいいのだと心中穏やかになった。これぞ太平洋の神秘、純白の砂浜に囲まれ、椰子の木が生い茂る大自然が醸成した、あの平和な純真無垢な女護ヶ島こそ、われわれだけの秘密にして、どんなことがあっても、他の人間どもに荒廃されてたまるもんか。
だが機会があったら、是非、もう一度ユックリと訪問したいものだ。他の同乗者も同じ思いだった。その後、もしパラオ~トラック島間を直行便するチャンスがあれば、いま一度、正確に位置を確認してみよう。どだい地図上に書かれてない島だから、頼りない地図をたよりに,感をたよるしかないのだ。
「シマッタ!こんなはずじゃない」いまごろ悔やんでみても、どう仕様もなかった。 こんなことなら、離水してゆっくりと上空を旋回して、島の特徴を確かめ、写真にでも収めておけばよかったのだ。何しろあのときは、三発エンジンの離水だったので離水距離が延び、旋回等している余裕がなかった。
それにしても何と同じ格好をした島の多いことか。間違ってへんな所へ着水したら、男ばっかりで、楽園どころか、地獄の一丁目だぞ。すべては後の祭りだった。
せめて現在のINS(慣性航法装置)があれば、正確な位置が観測できたのになぁ。そんなこといって、誰にも秘密の島を教えたくないので、下手な理屈を言い訳にしているんだろう。一人コッソリと、小型水上機をチャータ-する計画だろうと、疑っている人もいるでしょうね。
実はそうなんです。自分だけにこっそり教えてくれと頼まれれば私も年輩になって、訪れるチャンスもなくなったので、条件によっては、奥さんと相談して教えてしんぜますぞ、ウッフッフフ。 地球上唯一無二の不思議な楽園は、今も変わらない静かな孤島で、魅力たっぷりの美しい女性だけに護られていることを信じております。

大日本航空(㈱)の案内パンフレット