歴史にみる模型飛行機の顔さまざま
(1) 航空の実現を目指した試作研究の道具
歴史
1. はじめに
模型飛行機は、さまざまな顔を持っています。歴史的には時代ごとに一つずつ見せるのですが、現在の目には多くの顔が同時に見えます。
現在の顔の一つに、競技派の「模型飛行機」があります。これは、世の中一般には「模型飛行機」と呼ばれていますが、「模型」でも「飛行機」でもない場合があるのです。常識的な、国語辞典的な意味の「模型」は「実物の写し、雛形」です。ところが、現在の模型航空競技用の機体には、同じ形をした実物がありません。
形は異なっていても実物と同じ原理・機能で飛行するものは「機能模型」とされ、ゴム動力のライトプレーンが実例に挙げられます。そこまでは常識的な「模型」に含まれるのですが、実機に使われていない原理・機能で飛行するものが出現してきました。模型機は小型で、パイロットや燃料などの重量が少ないので、実機ではありえないほど翼面荷重と馬力荷重を小さくすることが出来ます。さらに、人体に対する加速度の制限が無いため、いくらでも急激な運動が可能です。だから、実機に存在しないような飛び方をする機体出現します。
実機の枠組みからの逸脱は進歩といえます。FAIが制定している模型機のスポーティング・コード(競技規則集)には、飛び方の原理・機能が限定されないように、「飛行機」と言う言葉は使われていません。呼称としては「The Model」と書いてあり、「当該模型」と訳していますが、文字通りの意味はなくなっていて、「当該飛翔体」くらいのきわめて広義の対象を指す言葉になっています。
また、FAIの「模型」の定義は下記のように「実物」の存在を前提としておらず、ヒトの搭載の可否や、全重量や翼面積の大きさなどの数値によって実機との線引きをしています。
「模型航空機とは、限定された大きさの、人を乗せることの出来ない、競技、スポーツ、レクレーション目的であり、商用、公共事業用、科学・研究用、軍用などの目的の無人航空機(UAV)ではないものを言う。」
「模型」航空機の定義については、常識的な解釈のほかに、競技の場合、法的な場合、損害保険付保の場合など、状況において個々に判断せざるを得ないのが実態です。一般に「模型飛行機」と呼ばれているものが、「模型」でも「飛行機」でもなくなってしまった経過やいきさつは、歴史を追っていくと明らかになります。様々な顔が順次出現し、模型飛行機の持つ多様性が分解されて表示されているからです
実物の飛行機、あるいは航空機産業が、多彩な科学技術を傘下に抱えた複雑なシステムであるように、模型飛行機もたくさんの要素を取り込みながら現在に至っています。だから、時系列で追うことは、模型飛行機の全体像を分析・理解するために、役に立つ観察法です。
2.「航空の実現を目指した試作研究の道具」という顔
模型飛行機の始まりをどこにするかと言う問題については諸説あります。たとえば、レオナルド・ダ・ヴィンチの機体は進化の区切りになります。また、4000年前のピラミッドから出土した「垂直尾翼がある鳥」の木像に起源を求める説もあります。本稿では、ジョージ・ケーリー卿のグライダー(1804年)から始めることにします。
現在、ヒトを乗せて飛行するものは「航空機」と呼ばれ、その方法によって飛行機、ヘリコプターなど一定の呼び方で細分されています。厳密に言えばこれから扱う飛行体は「模型航空機」でありケーリー卿の飛ばしたものは「模型グライダー」なのですが、当分は代表例として「模型飛行機」の名前で総称しておきます。この時代は「飛行機」と言う名称も定着しておらず、「飛行機械」、「飛行器」などさまざまな呼び方がされ、現在で言えば「航空機」に相当する意味を持っていました。
本題に入ります。最初に採り上げる模型飛行機の顔は、「航空の実現を目指した試作・研究を行なうためのモノ」です。要するに、地面を離れて飛行する仕掛けを作ることであって、目的はヒトを乗せるために考案された実機の試作と同じです。現在の模型飛行機は、実機の形や機能を写して、それを楽しむ目的が主ですが、この様な用途や考え方はまだありません。実機と同様に、飛行の実現という実用を目標とした学術研究の道具で、その点では実機との間の垣根は無かったわけです。
代表例として、次の3機を取り上げます。
*ジョージ・ケーリー卿(1773~1857)の模型グライダー(1804)
*ジョン・ストリングフェロー(1799~1862)の蒸気動力模型飛行機(1848)
*アルフォンス・ペノー(1850~1880)のゴム動力模型飛行機(1871)
年代も形式もさまざまですが、模型飛行機というくくり方では意味があるトリオです。後述しますが、近代になり模型航空競技が組織化されたとき、競技種目はグライダー、ゴム動力機、エンジン機に大別されました。それぞれの種目の直接的な起源をたどると、上記の3機に至るのです。
3. ジョージ・ケーリー卿(英)の模型グライダー
ジョージ・ケーリー卿(1773~1857)は最初の航空学者と言われています。カンバー(翼型の反り)のある翼型、迎え角と揚力の関係、揚力を発生させる大きな翼(主翼)と、その後方にある小さな安定のための翼(尾翼)の区分、重心位置、上反角、推力・抗力・揚力・重力の釣合い関係などを明らかにしています。
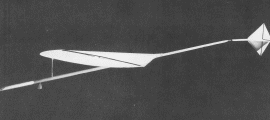
(図1)ジョージ・ケーリー卿の模型グライダー
後年(1853)に有人飛行に至っていますが、モデラーの視点からはその出発点となった模型グライダーが重要です。レプリカの写真に拠れば、細い矢軸のような胴体に主翼と尾翼が付いているだけの、余分な部分が全く無い構成です。主翼は、ホームベースの前側の両角を丸めたような形で、縦横比は小さく、尾翼は十字凧を直交させたような形です。尾翼の直前の胴体は、自在継ぎ手のようになっていて、ラダーとエレベータの角度を調整できるようです。
ケーリー卿は、当時の材料と構造の限界から、主翼の縦横比は小さくしなければならないと考えていたようで、この模型グライダー、後年(1853)に使用人を乗せて飛行したとされるグライダーともに凧に近い平面形です。後述するヘンソンとストリングフェローの機体の主翼は、今日的な目では手ごろな矩形翼ですが、これに対しては「縦横比が大きくて強度的に問題がある」というコメントを加えています。縦横比の大きな翼ほど効率が高いので、長年にわたって安定や構造の許す限り拡大されて、現在のグライダーの主翼縦横比は20を超えています。
イギリスのビクトリア朝は、科学が急速に進歩した時期です。上流階級では自邸に実験室を持つことがステータス・シンボルであり、社交界の女性の間でも、科学上の発明や発見が話題になったと言われています。ケーリー機の開発は、このような時代背景を持っていたわけです。
4. ストリングフェロー(英)の蒸気機関模型飛行機
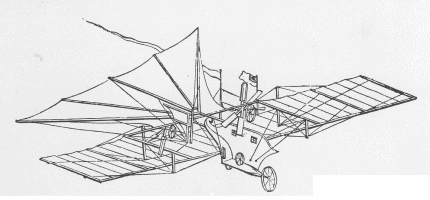
(図2)ヘンソンとストリングフェローの「空中蒸気車」(計画図)
ジョン・ストリングフェロー(1799~1883とウイリアム・サミュエル・ヘンソン(1812~1888)とは、ヘンソンが計画した大型の旅客機といえる「空中蒸気車」で協力したため、二人組で取り上げられます。1842年ころにスパン46m、翼面積418平方m、25~30馬力の蒸気機関という大型飛行機「空中蒸気車」を計画・設計し、特許を取り、事業化しようとしました。ロンドンとインドの間の定期便が計画され、エキゾチックな風景の上空を飛行する空中蒸気船のポスターが有名です。
この大計画を進める過程で、1844年から1847年にかけて、大小2機の模型機の飛行実験を行なっています。小型のものでも翼面積6.5平方mあり、空中蒸気車と同様に双発の推進式でした。ともに飛行できず、ヘンソンはアメリカに去ります。
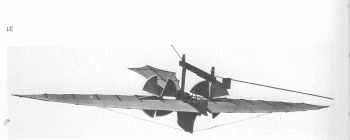
(図3)ストリングフェローの蒸気模型飛行機(ワイヤに懸垂されている)
その後、ストリングフェローは1848年にスパン10フィート、重量4kgの蒸気模型飛行機を作り、廃工場の建屋内で飛行に成功したと言われています。但し、ロープウエイ式にワイヤに懸垂して滑走させ、ワイヤが終わったところから3mの短い自由飛行を行い、カンバス・シートに着地させたと言う「飛行」でした。それでも動力付き模型飛行機の自力飛行の始まりとされています。
さらに、ストリングフェローは1868年にロンドンのクリスタルパレスで開かれた航空博覧会で、三葉機の公開飛行を行なっています。この機体は、重量が12ポンド(5.4kg)以下で翼面積28平方フィート(2.6平方m)、1/3馬力の双発と言われていますが、16ポンド(7kg)で1馬力と言う説もあります。時の国王陛下(エドワード7世)以下の観客の前で行なわれた初の動力模型飛行機の公開飛行でした。但し、資料によっては離陸失敗説もあり、ハリガネにつながれた繋留飛行でもあったために、完全な飛行ではなかったとする批判もあります。
5. アルフォンス・ペノー(仏)のゴム動力機
アルフォンス・ペノー(1850~1880)は1871年に、現在のライトプレーンに近い寸法・構造のゴム動力模型飛行機(「プラノフォア」と呼ばれた)を飛行させ、ゴム動力機の起源とされています。前後の時期にヘリコプターやオーニソプター(羽ばたき機)の飛行にも成功しました。それぞれの絵が複数枚残されており、レプリカも作成されています。ヘリコプターは、少年期のライト兄弟に影響を洗えたと言われます。
ペノーの業績は1892年に発表されたオクターブ・シャヌート(1832~1910、フランス系アメリカ人)の「プログレス・イン・フライングマシン」に詳しいのですが、数値はメートル法をヤード・ポンド法に換算したものであるので、元に戻してそれぞれの整合性を確かめて解読する必要があります。
シャヌート文献に拠れば、プラノフォア機の飛行は「131フィートを11秒で飛び」、「数旋回(several)して、ゴムが戻ってから出発点近くに軟着陸した」とあります。直線飛行距離ならば、地面を巻尺で正確に測定できますが、「3回前後の旋回飛行」の距離はモノサシでは測れません。131フィート=39.93mですが、「目測で40mくらい」と言うのがペノーが測った記録ではないでしょうか?「11秒」と言う時間も、ストップウオッチ測定ではなさそうで、誤差はあるでしょう。
ケーリー機、ストリングフェロー機に比べると何十年も後の飛行記録なので、定量的なデータが残されています。今日的な感覚ではかなりアバウトなものですが、航空力学の公式に当てはめてみると矛盾は無く、整合性があります。約40mを3旋回で飛行した場合、旋回半径は2m強で、車2台の駐車場所に収まるくらいのささやかな飛行ではあります。しかしながら、意図して制御した急旋回ですから、単に40m飛んだという記録よりは中身の濃い成果です。
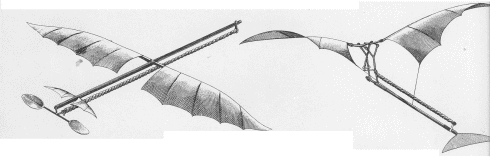
(図4)ペノーのゴム動力模型飛行機 「プラノフォア」(左)とオーニソプター(羽ばたき機:右)
ペノー機の仕様は次のとおりです。全長51センチ、主翼全幅(スパン)46センチ、プロペラ直径20センチ、機体構造重量16グラム、動力ゴム重量5グラム、翼面積4.9平方デシメートル。水平尾翼は旋回飛行のときに機首が下がらないように主翼に対して8度の上げ舵になっている。
6. ケーリーたちの「模型飛行機」が目指した実機
19世紀の、実物航空機が出現する前の「模型飛行機」には、お手本となる実物が存在しません。「模型」飛行機の目的も、現在のように楽しみのための作品ではなく、ヒトが乗る飛行を目指したデータ集めの予備実験でした。
ジョージ・ケーリー卿は、後日(1853)、ヒトが乗るグライダーを作って、プロンプトン谷を飛行させています。ストリングフェローの蒸気飛行機(1848)には、前置きとしてウイリアム・ヘンソン(1812~1888)との共同計画で「空中蒸気車」、「空中輸送会社」構想(1843)があり、それを目標とした縮小模型実験です。
ペノーの場合も実機を設計しており、可動な操縦翼面、引き込み脚、水陸両用機など、先駆的なアイデアが織り込まれていました。但し、ペノーのゴム動力模型飛行機(1871)は、前二者のように計画した実機(1876:無尾翼)と似ていません。
ペノーの時代になると、航空に関する論理のつながり、言い換えれば航空力学体系が出来つつあり、ゴム動力模型飛行機のデータを抽象して、異なった大きさ、異なった形の実物機の設計に役立たせる思考法が可能になったからだと思います。
手法はさまざまですが、ケーリー、ストリングフェロー、ペノー全て、模型飛行機を作った目的はヒトが乗る機体を飛行させるための手段であり、過程でした。現在時点で「模型」の国語辞典的な意味は実物の真似・雛形であり、実物の先行が前提になっています。ケーリーたちの「模型飛行機」は、実物が存在しなかったわけですから、その定義に当てはまるのでしょうか?
出典
図1、図3
The World of Model Aircraft by Guy R.Williams, 1973
図2、図4
The Encyclopedia of Model Aircraft by Vic Smeed, 1979
編集人より
大村和敏氏は元模型航空競技・ウェークフィールド級日本選手権者であり、模型航空専門誌にも寄稿されています。








