逓信省航空局 航空機乗員養成所物語
(26) – 民間航空の再開 –
歴史
民間航空の再開
1.「鶏明社」、「興民社」、そして「おおとり会」
終戦の年11月30日、田中不二雄は早くも代々木に「鶏明社」を設立した。かつての民間パイロットの元鳥人たちが、お互いに助け合い、誇りをもって切磋琢磨し、励ましていこうという主旨である。所沢陸軍飛行学校の側で飛行訓練校を経営していた彼は、自分の修理工場や格納庫の一部を代々木に運び込んだのである。
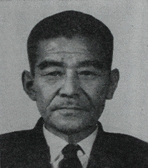
田中不二雄氏
彼は日本最初の飛行学校である伊藤飛行機研究所で操縦を学んだが、飛行適性がなく3等飛行機操縦士で終わっている。それでも航空界への絆を断ちがたく、昭和8年11月、自ら須崎の埋立地に田中飛行研究所を設立した。ちなみに彼の妻は、2等飛行機操縦士で女優でもある西村阜子である。
落ち込んでいる民間鳥人たちの憩いの場としての、鶏明社設立の意義は大きい。死線をさまよった乗員仲間のサロンのような所で、一泊10円の簡易宿泊施設も提供していた。利用者も徐々に増え、謄写版刷りの鶏明社報も発行した。「謎の隠密飛行」として、秘密裡に訓練を受け、朝鮮戦争の輸送業務に従事した、数人の元民間パイロットたちも、発信元は鶏明社である。
さらに終戦の年12月17日には、社団法人「興民社」が設立された。これは、かつての乗員養成所、大日本航空、大日本飛行協会が使用した、広大な土地や資材を処理するための法人組織である。朝日新聞社編集局長の美土路昌一(のち全日空社長)が会長、専務理事が中野勝義(のち全日空副社長)、渡辺尚次総務部長(のち全日空社長)の面々で、後の日本ヘリコプター、そして全日本空輸への人脈となった。
興民社が興した職種は多様で、農場経営、諸々の製品販売、機械工作工場、土木建築、トラック輸送、出版、記録映画等々で、民間航空再開後も、「鳩物産」「鳳文書林」「興民タクシー」として存続した。
鶏明社に集まった猛者たちは、全日本航空乗員調査会を発足、26年5月に設立された民間航空飛行団体「おおとり会」の礎となった。かつての乗員養成所の同窓会のようなもので、尾崎行輝名誉会長、川田幸秋会長、委員には糸永吉運(松戸中央1期、のち日航機長)や有働武俊(本科2期、のち全日空機長)、世話役として小池正一(米子3期、のち航大校長)らが名をつらねた。

川田幸秋氏
「おおとり会」の最盛期の会員は3,000名にもなったが、赤字の増大と共に、5年後に日本青年飛行連盟に吸収合併された。しかし、やがて誕生する日本人の手による航空会社の運航乗務員として、貴重な人材になったことはいうまでもない。
2. 民間航空の再開
昭和25年6月25日、突如、北朝鮮軍歩兵師団による、ソ連製T34戦車を先頭とする機動部隊の南進によって、朝鮮戦争が勃発した。以来、約3年間の騒乱が続いたが、皮肉にもこれを契機として、日本の航空禁止政策が緩和された。6月26日、SCAPIN2106「日本国内航空輸送事業運営に関する覚書」が日本政府へ指令された。
それまで鍋釜や精々オートバイなどを作って、かろうじて糊口をしのぐタケノコ生活を送っていた、かつてのヒコーキ野郎たちは、連合軍の軍需に応じる必要から、久々に生き返った。戦火の中で必死に身に着けた飛行機、発動機、航空計器に関する優秀な製作技術ないし整備技術は、米軍機の修理ないし整備、軍需品の生産と、にわかに活気づいたのである。
戦争特需による恩恵は、13億ドル(約4,680億円)といわれている。これを契機に日本経済は上昇したが、同時に、農業耕作機械の整備、漁村での船舶の整備運用、さらにラジオ、時計、その他各種精密機械の整備運用と、その波及効果は予想以上のものがあり、民間航空再開の気運が膨らんでいったのである。
昭和27年7月に航空法が公布・施行、翌月には運輸省航空局が開局、運輸省外局だった航空保安庁が発展的に解消され、競って航空会社設立申請がおこなわれた。それは日本航空をはじめ、日本ヘリコプター、極東航空、それに青木航空、中日本航空、日東航空、富士航空、北日本航空、東亜航空など16社にもおよんだ。
3. 日本航空㈱設立
将来の日本人の手による民間航空会社設立を早くから目論んでいた松尾静磨航空保安部長らの尽力で、26年8月1日、資本金一億円の日本航空㈱が誕生した。営業は日本人が担当したが、日本人パイロット不在であり、運航はノースウエスト航空傘下のトランス・オーシャン航空(TALOA航空)が請け負った。

松尾静磨氏
待ちに待った航空再開に、意気揚々と日本航空に入社したかつての鳥人たちは、意に反して、パーサー業務を強いられる苦渋の門出になった。客室乗員をやりながら、TALOA航空の運航技術を学べ、というのである。6年間の航空界の空白を埋めるべく、周囲の有象無象の圧力に耐えながら、米国の運航方式を少しでも吸収すべく、彼らは必死で頑張った。
パーサーとして乗務した者は、長野英麿(日本飛行学校)、江島三郎(海委3期)、諏訪義勝(陸委14期)、尾崎行良(養成所9期)、水間博志(養成所10期)、小田泰治(亜細亜飛行学校)、関山哲雄(海委15期)、工藤哲(名古屋飛行学校)、富田多喜雄(海委16期)、片岡孝、木本栄司(陸委18期)、大坪憲三(仙台長1期)、糸永吉運(松戸中央1期)、野間聖明(仙台1期)らの顔ぶれである。
そのほとんどが、かつての陸海軍依託生ないし乗員養成所出身者である。「日航は人相の悪い男が機内サービスをしている」と、事情を知らない乗客に皮肉を言われながら、サービスに勤め、心無い米人パイロットに嫌われながら、コックピットへ出入りして、米国式運航方式を必死で学びとっていった。
雲中の着陸アプローチで、高度300や400フィートで、突然、目の前に滑走路が現れるのが、何かマジックでも見ているような錯覚を覚えながら、6年間の航空空白時代を思い知らされた。
戦時は敵性語として排斥していた英語の習得と同時に、米国式の民間航空規則(CAR)や連邦航空法(FAR)に基づいた、できたばかりの航空法や航空工学の習熟、航空機材の勉強、出発前の飛行計画の作成、航法や運航管理(ディスパッチャー)業務、計器飛行方式のマニュアル作り、ADF(自動方向探知機)などの、航法援助施設の知識等々、しなければならない勉強は山ほどあった。歯を食いしばって頑張った彼らの努力の成果は、その後の日航運航部門の礎となっていったのである。
4. 日本ヘリコプター㈱設立
日本ヘリコプター(日ペリ)が設立したのは昭和27年12月である。前掲の興民社を立ち上げた美土路昌一、岡崎嘉平太、中野勝義、元中華航空上海支社長の鳥居清次、元満州航空の川端清一、渡辺尚次らが中心になって、今の航空会館4階に事務所を設けて準備を進めていった。鳥居清次(後、全日空専務)は、昭和7年にバーモン・トロフィーを授与されている。

美土路昌一氏
最重要課題の一つであるパイロットの確保が大変だった。元大日本航空パイロットの大半は日航へ入っていたから、神田好武(陸委16期)は、某ゴム会社のチャーターを請負い、購入したばかりのヘリコプターを駆って全国を飛び歩き、「地下足袋」の宣伝をしながらパイロットを集めたという。
岡嘉吉(国粋義勇飛行隊)、深牧安生(陸軍操縦学生)、野寺誠次郎(海委6期)、石田功(陸委12期)、大堀修一(海委10期)、森和人(松戸中央1期)、飯塚増次郎(仙台6期)、細淵昇(仙台8期)、それに室原博(学連)らが集まってきた。
日ペリとほぼ同時期に、日本航空輸送の先駆けを創った井上長一は、関西汽船などと協力して極東航空を立ち上げていた。この2社が定期航空便を飛ばすようになったのは、昭和29年春からである。大阪から西側が極東航空、東側が日ペリとし、機体は両者共に、デハビランドDH104方「ダブ」を使用した。

井上長一氏
運営はまさに赤貧洗うがごとき毎日で、日ペリは「日減り航空」、極東航空は「極道航空」と揶揄されながらの経営は、飛行機の燃料代にも事欠く有様であった。とくに極東航空はハンドレページ・マラソンという欠陥機によって息切れ寸前の状態に追い込まれた。
運輸省の行政指導により、昭和33年3月、両社が合併、全日本空輸㈱として生まれ変わった。直後の8月12日、ダグラスDC3型旅客機の伊豆南東海上での墜落事故により、乗員乗客36名が死亡した。まさに倒産寸前の状態に追い込まれ、もっとも苦しい時代だったが、美土路社長の「現在窮乏、将来有望」を合言葉に、全社員一丸となって再建に取り組んでいったのである。
逓信省航空局 航空機乗員養成所物語リンク
(1) シリーズ開始にあたって
(2) 民間パイロット養成の萌芽
(4) 航空輸送会社の誕生
(5) 民間パイロットの活躍
(6) 草創期の運航要領
(7) 航空機乗員養成所の設立(その1)
(8) 航空機乗員養成所の設立(その2)
(9) 航空機乗員養成所の訓練概要
(10) 天虎飛行研究所の実状
(11) 中央航空機乗員養成所の設立
(12) 予備役下士官の評価と制度の変遷
(13) 地方航空機乗員養成所本科生制度
(14) 戦時下の本科生の動向
(15) 大日本航空の組織改編
(16) 海軍徴用輸送機隊の編成
(17) 陸軍直轄の航空輸送部隊
(18) 航空機乗員養成所卒業生の葛藤
(19) 予備役下士官パイロットの戦場
(20) 乗員養成所第14期操縦生の青春
(21) 乗員養成所卒業生の特攻
(22) 愛媛乗員養成所第14期生の特攻
(23) 陸軍知覧特攻基地
(24) 「赤とんぼ」特攻の悲劇
(25) 終戦と大日本航空の解散
(26) 民間航空の再開
(27) 戦没者の慰霊








